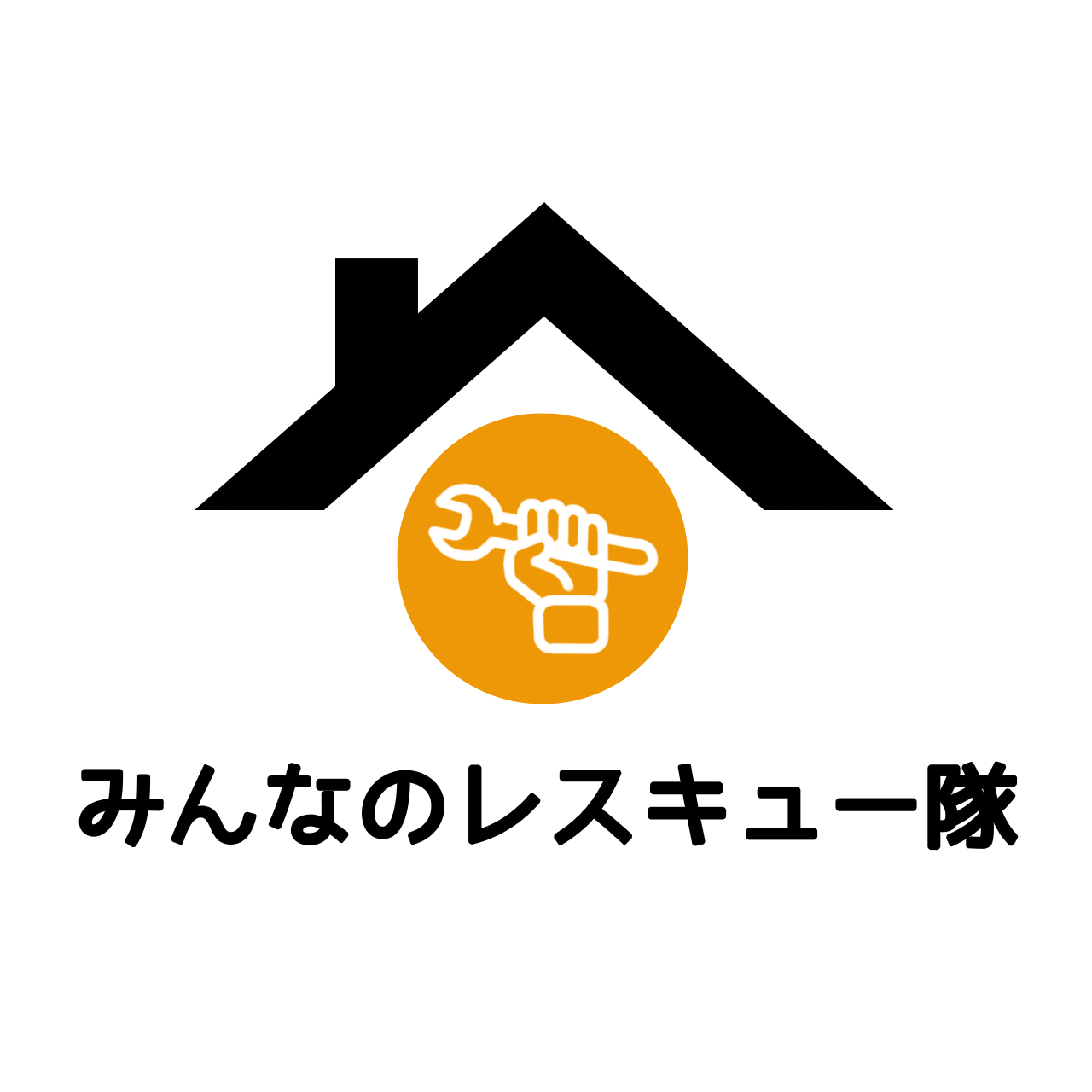冬眠しないハクビシンは、一年を通して目撃される害獣です。ハクビシンは建物にわずかな隙間があれば侵入し、屋根裏を住処とします。天井からドタドタと動物の足音がする場合は、ハクビシンが住み着いているかもしれません。愛らしい外見を持つものの彼らの糞尿は悪臭や家屋が劣化する原因になり得ます。また果実を好んで食べるため、農作物への被害が後を絶ちません。
本記事ではハクビシンを見つけた際の対処法や追い出し方、やってはいけない行動について解説。ハクビシンは勝手に駆除してはいけないため、市役所など自治体への連絡が必要です。適切に捕獲・駆除するために、ぜひ本記事を参考にしてください。
ハクビシンを見つけた際にやってはいけない行動
鼻筋にすっと通った白いラインとスリムな見た目から、愛らしい印象を受けるハクビシン。大柄な猫程度のサイズ感のため、近づいてみたくなるかもしれません。しかし野生動物はペットとは違い、人馴れしていないため近づくことは禁物です。
ここでは、ハクビシンを見つけた際にやってはいけない行動を紹介します。
近づいたり触ったりする
ハクビシンは可愛らしい見た目をしているため、ついつい近づいて触ったり観察したりしたくなるかもしれません。しかし野生動物のハクビシンは寄生虫や細菌を保有している可能性が高く、健康被害をもたらすなど衛生面が心配です。
また、触ろうとすると攻撃してくる危険性も否定できません。噛みつかれた際にできた傷口から寄生虫や細菌などが侵入し、感染症にかかるリスクもあります。ハクビシンを見つけたら、むやみに近づいたり触ったりしないようにしましょう。
餌付けする
ハクビシンに限らず、野生動物にエサを与えてはいけません。簡単に食べ物をもらえると、度々現れるようになったり近くに住み着いたりしていまいます。
ごみを漁ることもあるため、家庭ごみを捨てる際はハクビシンに荒らされないように気をつけましょう。またハクビシンは犬などペットのエサを食べることもあります。室外にペットのエサを置いている場合は、放置せずに都度片づけましょう。
自分で捕獲したり駆除したりする
害獣であるハクビシンですが、鳥獣保護管理法による保護対象の動物でもあります。
ただし完全に捕獲を禁止しているのではなく、都道府県知事から許可を得た人であれば捕獲が可能です。
さらに捕獲した場合には、駆除や死骸の処理まで個人が行わなければならないケースもあります。そのためハクビシンを見つけても、勝手に捕獲・駆除しないようにしましょう。
【画像付き】そもそもハクビシンとはどんな動物?

野生動物を庭や屋根裏などで発見しても、一目で何の動物か判断することは難しいものです。しかし住み着いた動物を追い出すには、動物の特定が欠かせません。ハクビシンはどのような特徴がある動物か、事前に知っておきましょう。
ハクビシンの特徴
名前の由来でもある、額から鼻にかけて通る白い筋がハクビシンの特徴です。ハクビシンは全体的に灰色味を帯びた茶色の体毛をしており、大きめの猫くらいのサイズです。鳴き声も「キュー」「ミャー」など猫に似ています。
夜行性のハクビシンですが、夕方や朝方の時間帯に活動をすることもあります。民家の屋根裏や倉庫をねぐらとするため、深夜や朝方に天井からドタドタと走り回る音がすることも。夜中に天井から騒音がする場合は、ハクビシンが潜んでいるかもしれません。糞は長くて丸い形をしており、果物の種子が混ざっていることがあります。
ハクビシンとアライグマの見分け方
ハクビシンと似た灰褐色の体毛を持つ動物に、アライグマがいます。見分けるために役立つ、それぞれの特徴をまとめました。
| ハクビシン | アライグマ | |
|---|---|---|
| ジャコウネコ科ハクビシン属 | アライグマ科アライグマ属 | |
| 体長・体重 | 40~60cm・2.0~5.5kg | 40~65cm・3.5~11.0kg |
| 尾 | 長いのが特徴 | 黒色の縞模様が5~7本ある |
| 足跡 | 足裏は長く、指は短く丸い指は5本 | 足裏は長く、指も長い指は5本 |
| 糞 | 種子を含んでいることが多い | 骨を含んでいることがある |
どちらも雑食の動物ですが、ハクビシンは甘い果実を好み、アライグマは小動物を好みます。そのため糞の内容物から見分けることも可能ですが、感染症のリスクがあるため素手で糞を触らないようにしましょう。
ハクビシンを見つけて放置することで発生する被害とは?
個人での捕獲が禁止されているからといって、ハクビシンを放置しておくのは禁物です。家屋に住み着いたハクビシンをそのままにおくと、どのような被害を被るのでしょうか。
ここで紹介する事象に心当たりがある方は、すでにハクビシンが侵入している可能性を否定できません。屋根裏がハクビシンの住処になっていないか確認してみましょう。
住宅の劣化
ハクビシンは、同じところで繰り返し糞尿をする習性があります。ハクビシンが屋根裏に住み着くと、溜まった糞尿が木材に染みこみ腐食する原因となります。そのため雨漏りが原因と思っていた天井のシミが、ハクビシンの糞尿によるものだったというケースも稀ではありません。
騒音による精神的なダメージ
夜行性であるハクビシンは、夕方から朝方にかけて活動します。天井からする足音や鳴き声は家の中が静まる夜中には特に聞こえやすく、騒音が気になり眠れないことも。睡眠不足が続くことでストレスや疲労が溜まり、体調を崩す方も少なくありません。
衛生状態の悪化
野生動物の体や糞には、ノミやダニなどの害虫やウイルスなどが潜んでいます。ハクビシンの糞を放置することは悪臭が漂うだけでなく、糞やダニを介した感染症のリスクがあります。
ハクビシンの糞による影響は、ペットにも起こるため注意が必要です。ハクビシンの糞中にいる寄生虫やウイルスは、子犬が罹患すると重症となり得るジステンパーやパルボウイルス感染症の原因となります。
農作物の食い荒らし
雑食であるハクビシンは、昆虫や魚、植物など幅広く食べますが、果実を好みます。木登りが上手なこともあり、ももやぶどう、りんごなどの果樹園での被害が多く報告されています。2016年にはハクビシンによる農業被害額が4億円以上と報告されており、農作物への被害は深刻です。庭に植えてある柿の木なども、被害にあうため注意が必要です。
果実以外にもトウモロコシやジャガイモ、トマトなどの農作物も食べるため、家庭菜園でも被害にあうケースは十分にあります。
火災の原因を引き起こすことも
野生動物が引き起こす火災の原因として、げっ歯類であるネズミが電気コードをかじることが挙げられます。ハクビシンはげっ歯類ではないため、何でもかじる習性はありません。しかし犬や猫と同様に、コードをおもちゃにしたり歯の生え代わり時期に噛んだりします。そのためハクビシンが電気コードをかじり、漏電火災を引き起こすこともあります。
ハクビシンを見つけた時の対処法
ハクビシンは季節を問わず1年に1回、2~3頭を出産します。そのためハクビシンを見つけたら、早めに捕獲して数を増やさないことが重要です。農作物を荒らされるなど実害がある場合はもちろん、敷地内でハクビシンを目撃するようであれば、早急に対応する方が得策です。
自治体に連絡する
前述したように、ハクビシンは個人が勝手に捕獲してはいけません。そのためハクビシンを見つけたら、まずは自治体に連絡しましょう。
自治体によっては、ハクビシンを捕獲するための箱わなを無料で貸し出しているところもあります。箱わなの使用には制約もあるため、事前に市役所など自治体のホームページで確認しておきましょう。
専門業者に駆除を依頼する
自治体による箱わな貸出は、期間や回数が決まっています。また自分で捕獲状況を確認したりエサを交換したりしなければなりません。自治体によってはハクビシンを捕獲できた場合に、処分も自分でする必要があることも。死骸であればまだしも、生きているハクビシンを素人が処分することは難しいでしょう。
野生動物の捕獲をしたことがない方は、専門業者へ任せる方が安心です。駆除だけでなく、再び家屋に侵入してこないよう防除対策を行ってくれる業者もあります。ハクビシンは500円玉ほどのわずかな隙間でも侵入できるため、プロに対策を依頼するのが得策かもしれません。
ハクビシンを寄せ付けないための対策
ハクビシンは雨どいを登ったり電線を渡ったりすることができるほど、運動神経が高い動物です。また頭が入る大きさであれば、どこにでも侵入することができます。そのためハクビシン対策としては、家に侵入させないことが重要です。
まずは、侵入口となる穴を塞ぐことから始めましょう。登ることが得意なハクビシンは軒や雨どいの穴からも簡単に侵入します。家屋の高い位置にある穴にも、金網を設置するなど対策が必要です。
その上で、ハクビシンが苦手とするものを使用した対策を講じましょう。ハクビシンは嗅覚が優れているため、刺激的なニオイが苦手です。侵入口付近に唐辛子や木酢液、市販の忌避剤を設置したりしましょう。
詳しくはこちらの記事で害獣の追い出し方を解説しています。ハクビシン以外の害獣についても紹介しているので、参考にしてみてください。
関連記事:屋根裏にいる動物の侵入口とは?徹底的に侵入を防止して追い出す方法まとめ
ハクビシンに関するQ&A

ハクビシンを捕獲したり追い払ったりする前に知っておきたい疑問にお答えします。
ハクビシンの正しい危険性を知り襲われた時の対処法を事前に把握することで、ハクビシンを見つけた時に慌てずにすむでしょう。
ハクビシンを見つけたら自分で対処せず専門家に相談しよう
ハクビシンが住み着き糞尿による天井のシミや悪臭に悩まされている場合は、早急に駆除しなければなりません。しかしハクビシンの捕獲には許可が必要ですし、襲われて怪我をする危険性があります。そのため害獣駆除に慣れた専門業者に依頼するのが、安心です。中には侵入予防の対策を講じてくれる業者もあります。
当サイトでは、信頼できる害獣駆除業者を紹介しています。業者選びに迷っている方は、ぜひ参考にしてみてください。