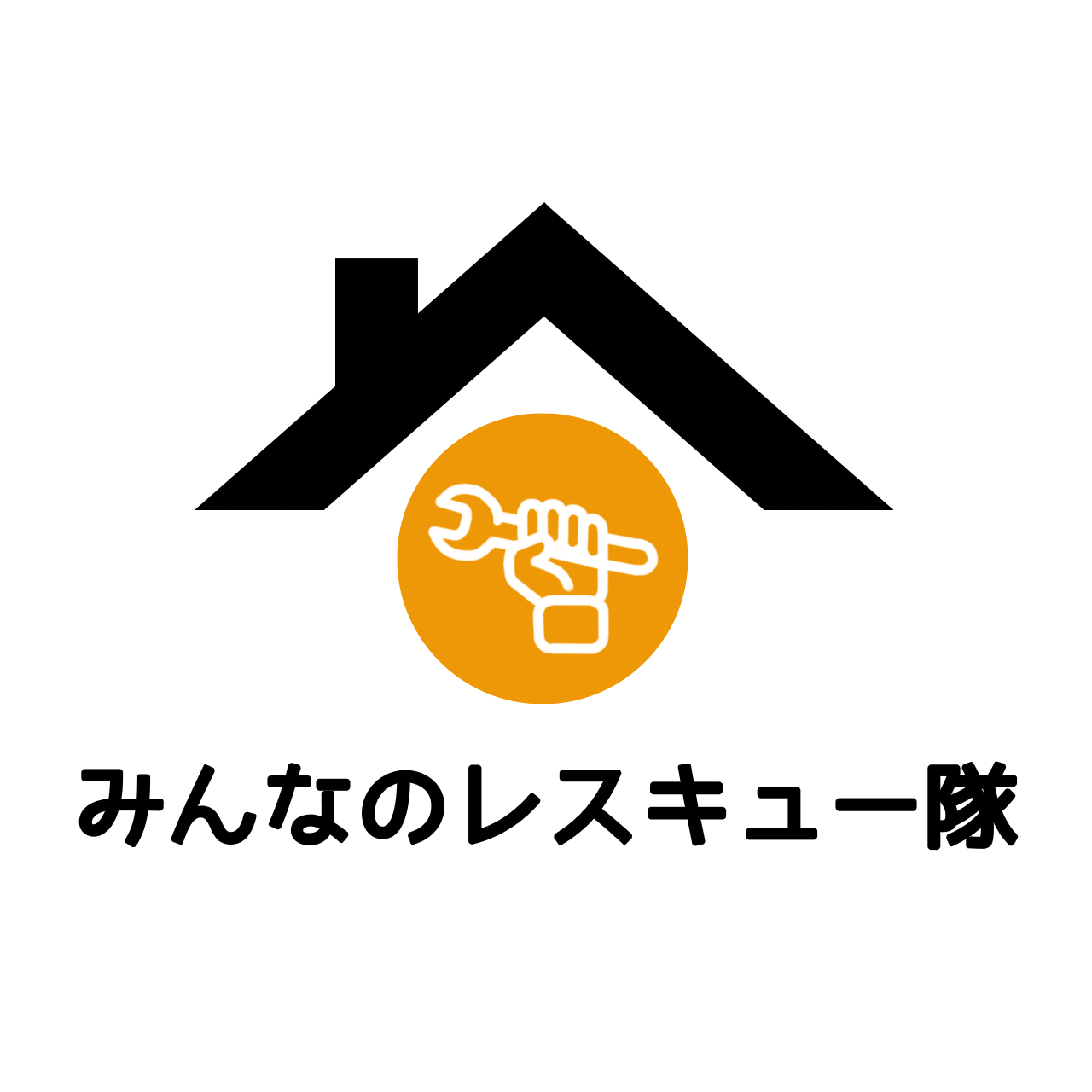冬場は家屋に被害を及ぼすシロアリをあまり見かけず、食害の心配がないのではとホッとひと息つきたくなる時期です。しかし油断は大敵。冬場のシロアリを放置するといつのまにか繁殖して被害が拡大し、手遅れになるかもしれません。この記事ではシロアリの生態や冬場でもシロアリがいる家の特徴を解説し、本格的な被害を避けるために家庭でできる対策をお伝えします。シロアリ駆除を業者に依頼する際の選び方のコツも紹介しているので参考にしてください。
シロアリは冬眠せず冬の間も活動している!
シロアリは暖かい季節に活発に動き回り、寒い季節は床下や木材などの隙間で静かに活動します。気温が低くなると動きが止まる、または極端に鈍くなりますが冬眠はしません。シロアリの死滅温度が気になる方も多いでしょうが、人が暮らせる温度環境であればシロアリも生きていけると考えて良いでしょう。
日本には20種類を超えるシロアリが生息しています。なかでも家屋に被害を与える代表的な種類がイエシロアリとヤマトシロアリです。
イエシロアリ
イエシロアリは比較的寒さに弱い種類で床下や土中だけでなく屋根裏にも巣を作り、主に地下道を通り地下から屋内へ侵入します。新材を好み食欲が旺盛のため、建物全体へ被害を及ぼすこともある危険なシロアリです。
<エシロアリの生態>
| 生息エリア | 千葉県より西または南の沿岸部や四国、九州の内陸 |
|---|---|
| 活動温度 | 10℃前後(好適温度は30~35℃) |
| コロニーの規模 | 100万匹を超えるケースもある |
| 群飛期 | 6月~7月の夕方から夜にかけて |
ヤマトシロアリ
ヤマトシロアリは家屋に被害を及ぼすシロアリの約8割を占め、比較的寒さに強く、餌場を巣として生活するのが特徴です。湿った木材を好み、水廻りに発生しやすい傾向があります。
<ヤマトシロアリの生態>
| 生息エリア | 北海道北部をのぞく日本全土 |
|---|---|
| 活動温度 | 6℃前後(好適温度は12~30℃) |
| コロニーの規模 | 数万~十数万匹で形成 |
| 群飛期 | 4月~5月の昼間 |
冬の間にシロアリが生息しやすい場所

シロアリは春先から初夏にかけて羽アリの群飛シーズンを迎え、夏から秋の気温が高い時期に旺盛な食欲を発揮します。冬場は目にする機会が極端に減りますが、活動は続けているのがポイントです。では冬場のシロアリは主にどのような場所にいるのでしょうか。注意したいのは、湿気が多い場所と暖かい場所です。
結露による水たまりができている場所
シロアリは湿り気のある木材から栄養と水分を摂取します。そのため、家のなかでは結露や水溜まりができるような湿った場所に注意しましょう。
- 窓枠付近
- ベランダへの出入り口
- 勝手口
シロアリはこのような場所に発生しやすい傾向があります。特にヤマトシロアリは湿って腐った木材や朽ちた木をエサとして好み、そのまま生息する習性があるため警戒が必要です。
暖房器具を置いている場所
イエシロアリは暖かい環境を好む習性があり、ヤマトシロアリも移動しながら暖かくてエサを確保できる場所を巣とします。そのため、冬場は暖房器具を置いている暖かい部屋も注意が必要です。
- リビング
- 寝室
- 脱衣所
- お風呂場
室内でも特に上記はシロアリが発生しやすい場所です。近年の住宅は基礎の外側に断熱材を施す基礎外断熱工法をはじめとした機密性が高い造りが多く、冬場でも暖かいことに加えて外敵が侵入しにくいためシロアリにとって快適な環境だと言われています。
冬場のシロアリ対策
冬場のシロアリ対策では徹底した湿気対策が大切です。シロアリが心配なご家庭は、被害を避けるために定期的な換気と結露対策を行いましょう。ただし、ここで紹介するのは簡易的な予防策で根本の解決にはなりません。本格的なシロアリ被害が見られるときは専門業者へご相談ください。
定期的に換気する
シロアリは湿度が高く暖かい場所を好みます。冬場は乾燥するから大丈夫と思われがちですが、気密性の高い家や加湿器を使う家庭では湿気がこもっている場合も……。こまめな換気を心がけ、室内に湿気を溜めこまないことが大切です。
定期的な換気のほか、以下のような対策も有効です。
- 室内用の除湿剤を活用する
- 換気口の周りにある家具や荷物を片付ける
- 壁に接した家具を少し話して空気の通り道を作る
結露を放置しない
冬場は寒い外と暖かい室内の温度差で結露が発生しやすく、水回りだけでなく窓やベランダ、玄関ドア付近もカビや腐食のリスクが上がります。シロアリが集まりやすい環境を作らないよう、結露を見つけたら放置せず水分を拭き取りましょう。部屋の隅や押し入れ、クローゼットなども注意が必要です。
シロアリの活動が活発になる前に本格的な対策が必要
冬場はシロアリを見る機会が減るため油断しがちですが、床下などの目立たない場所で活動し続けています。シロアリ駆除は、羽アリが一斉に飛び立つ4月〜7月にかけて依頼が増える傾向がありますが、冬場でも可能です。本格的に暖かくなる前にシロアリ駆除を依頼すると下記のようなメリットがあります。
冬場のシロアリ駆除におすすめな業者の選び方
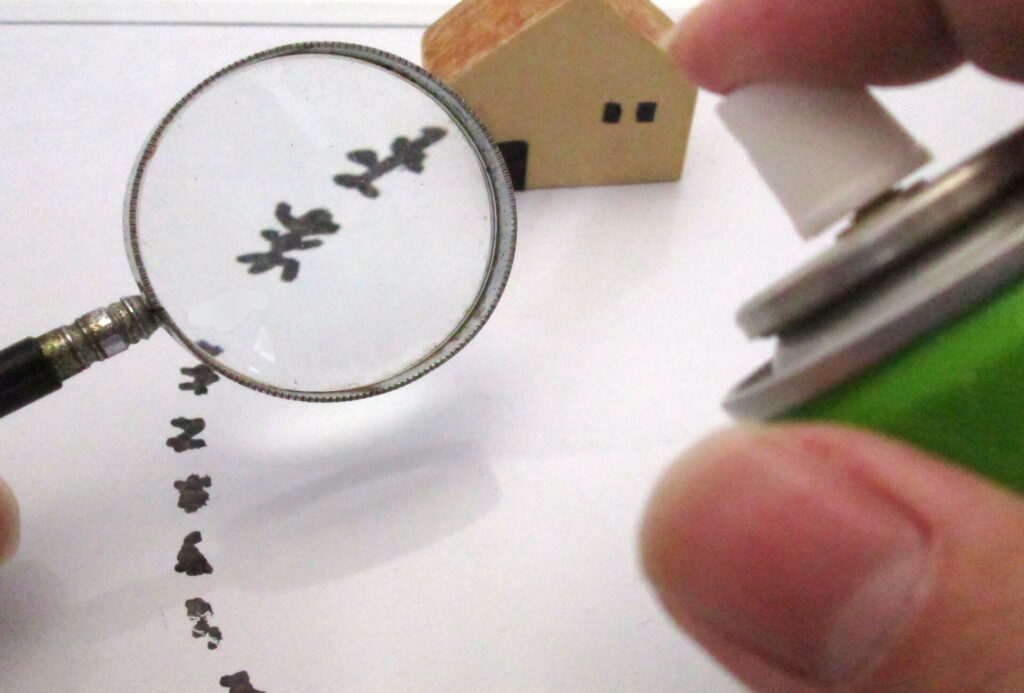
シロアリ駆除をプロに依頼する際は、信頼できる業者選びが大切です。選び方としては、資格の取得有無を参考としたり、見積り内容やアフターサービスを確認する方法があります。初めから1社に絞らず、数社から見積りをもらい比較すると価格面でも満足できるでしょう。
しろあり防除施工士が在籍している
シロアリ駆除は床下や壁裏など目が届きにくい場所での作業となり、依頼主が常に作業を確認できるわけではありません。家屋の基礎に関わる作業のため、ノウハウとともに高い施工技術が求められます。そのひとつの指標となるのが「しろあり防除施工士」の取得有無です。シロアリ駆除において資格は必須ではありませんが、「しろあり防除施工士」がいる業者を選ぶと一定の技術が担保され、安心材料の一つとなります。
見積りが明確・見積り後のキャンセルが無料
シロアリ駆除業者を選ぶ際は事前に見積りを依頼し、工程ごとの単価やトータル金額、追加料金がかかる可能性を確認します。「一式」のような表現がある場合は内容を詳しく聞きましょう。
複数社から見積りを取り、作業内容と価格のバランスがとれた業者を選ぶのがおすすめです。見積もりを依頼する際は、見積り後のキャンセルが無料かどうかも確認しておきましょう。
アフターサービスが充実している
シロアリ駆除で使用する薬剤の有効期間は5年間が目安と言われています。その間のアフターサービスの有無や、サービスの充実度も調べておきましょう。アフターサービスが有料の場合は、内容と金額のバランスを見つつ予算に合う業者を検討します。
冬場のシロアリの活動に関するQ&A
シロアリが冬場どのように活動しているか、よくある質問と回答をまとめました。シロアリの生態について知るキッカケとしてご確認ください。
冬だからと油断せずにシロアリ対策をしよう
シロアリは寒い時期は極端に見かける機会が減りますが、1年中活動しています。暖かく湿った場所が大好きなシロアリにとって気密性が高い住宅は格好の住処。冬だからと油断せず、対策を講じて発生予防に努めましょう。家に住みつくとコロニーと呼ばれる集合体として繁殖し、集団で広範囲に渡り家屋に被害を与えるため、もし見つけたらプロの手で駆除してもらうのがおすすめです。シロアリ駆除業者を選ぶ際は複数社から見積りを取り、資格の有無なども参考に信頼できる先を選びましょう。当サイト掲載の業者もぜひご検討ください。