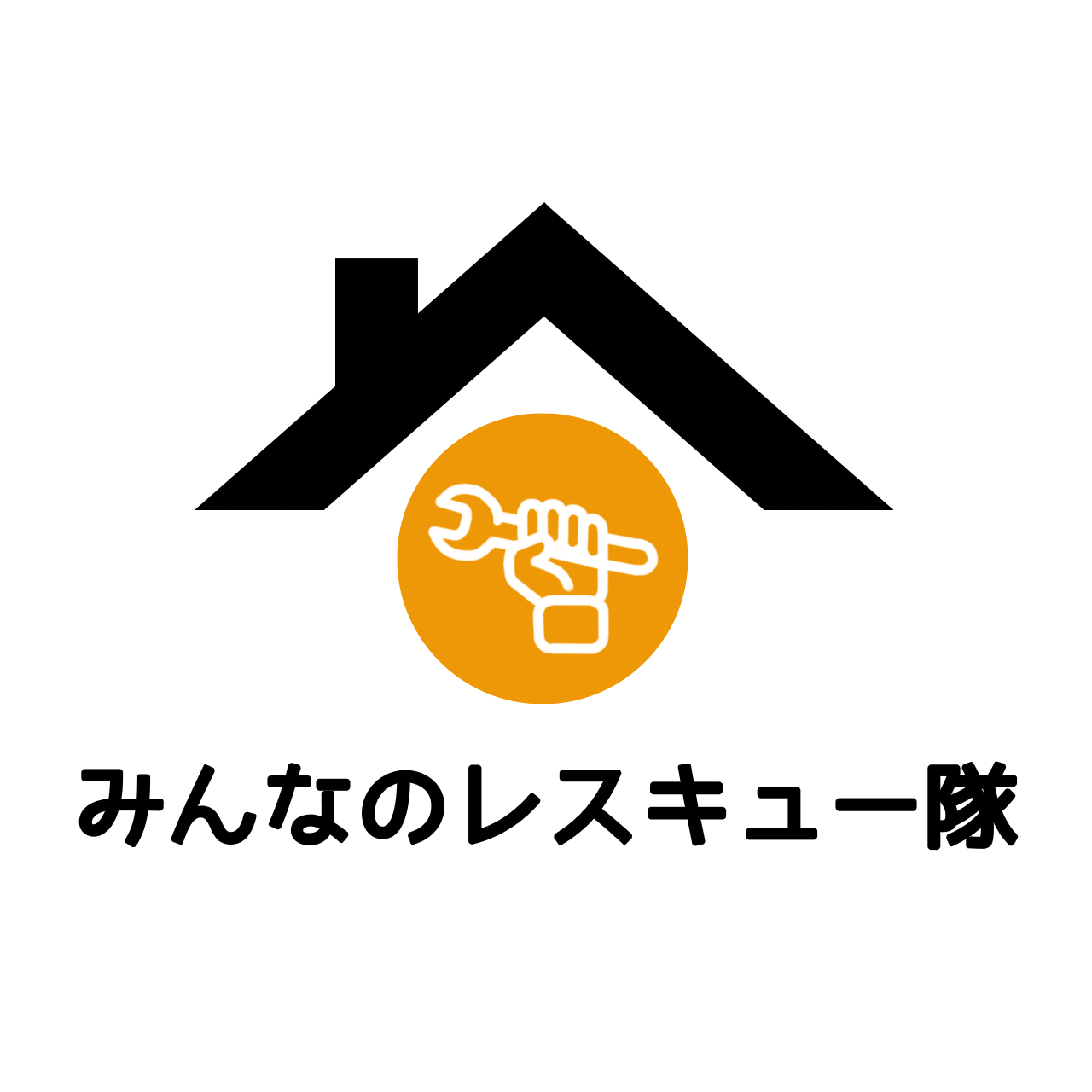「屋根のほうからドタドタ、トン、キュッキュという音が聞こえる」「屋根裏に同じ形の糞がたくさん落ちていた」「部屋全体が臭くなった気がする」。これらが当てはまる場合、屋根裏に害獣が侵入しているかもしれません。一見かわいらしい見た目のハクビシンやアライグマ、たぬきなどの動物は、家屋の被害や健康被害を引き起こす「害獣」です。いち早く、そして的確に対処するためにも、まずは侵入した動物を特定しましょう。本記事では屋根裏に住み着きやすい動物の特徴を詳しく解説。活動時間帯や音の特徴をもとに害獣を見分け、追い出す方法を紹介します。
屋根裏からドタドタと音がしたら害獣の侵入を疑うべき
急に屋根裏から音がすると、「なにが潜んでいるんだろう」と不安になってしまいますよね。屋根裏から異音が聞こえた場合、害獣の侵入を疑いましょう。害獣(がいじゅう)とは文字通り、人間に害を及ぼす動物のことで、日本では近年害獣による被害が加速しています。害獣のなかでも、屋根裏に侵入するものとしては下記が挙げられます。
- ネズミ
- イタチ
- たぬき
- アライグマ
- ハクビシン
- コウモリ
ネズミやコウモリといった小さな動物だけでなく、イタチやアライグマ、ハクビシンなどの中型以上の獣も屋根裏を好みます。土台や柱などを食い荒らして家屋を脆くするのはもちろん、ふん尿による悪臭、さらには病原菌の媒介とさまざまな被害をもたらすのです。
【時間帯別】屋根裏に侵入した害獣の見分け方
多くの害獣は夜行性で人間が寝ている時間帯に行動しますが、まれに朝や昼間などの日中に姿を見せる種類もいます。害獣を追い出すためには、それぞれの種類にあった対策を講じることが必要です。
ここでは、屋根裏に侵入した害獣の見分け方を活動する時間帯別にチェック!どの時間帯に音がするのかをもとに、住み着いた害獣を特定していきましょう。
朝に活動する害獣
深夜から明け方にかけて活動する害獣の場合、朝になっても活動していることがよくあります。とくに、夜明けが早くなる夏場はハクビシンが餌を求めて活動している姿がたびたび目撃されています。日没から夜明けにかけて活動するネズミも、朝型に活動する害獣のひとつです。住み着いている害獣の数が増えると、朝に活動する個体も増えやすくなります。
昼に活動する害獣
多くの害獣は日中眠っていますが、季節によっては昼に活動する場合もあります。とくに、冬眠をしないイタチやアライグマなどは、寒い冬場には夜間の活動量が減り、反対に日中に餌を求めて動きやすくなります。また、ネズミは学習能力や記憶力が非常に高いため、人間がいない日中を狙って活動するケースも。このように、夜行性と言われる害獣であっても昼に活動する場合があるのです。
夜に活動する害獣
屋根裏に住み着く害獣のほとんどが夜間に活動します。とくに、たぬきやイタチ、日没前後に活動するコウモリは暗くなってから活動をはじめる害獣で、日没前後から真夜中、明け方にかけて長時間動き回ります。
また、多くの害獣が繁殖・出産シーズンを迎える冬の終わりから春にかけては、求愛行動や出産準備に伴う巣作り、餌の蓄えなどのために、夜間の活動が活発化。ねぐらとしている屋根裏だけでなく、周囲の路上や庭などでも目撃されやすくなります。
| 活動する時間帯 | 季節による変化 | |
|---|---|---|
| ネズミ | 夜間、とくに日没後約1時間と夜明け前。 | 冬眠はしないが寒さに弱く、冬場は活動量が減少する。基本は夜行性だが、人家に住み着いている場合は日中活動するケースも。 |
| イタチ | 日没から夜間にかけて。 | 冬眠はせず、年中活発に活動する。繁殖期の春ごろに活動量が増える。 |
| たぬき | 日没の少し前から夜明け前まで。 | 冬眠はしないが、冬場は活動量が落ち、日中も活動しやすくなる。 |
| アライグマ | 日没の少し前から夜明け前まで。 | 冬眠はせず、年中活動している。繁殖期を迎える春は日中も活動する。 |
| ハクビシン | 日没の少し前から夜明け前まで。 | 寒さに弱いため、冬場は日中の活動量が増加。夜間はねぐら付近で休んでいることが多い。 |
| コウモリ | 日没の少し前から2時間程度。 | 11月半中旬から3月頃にかけて冬眠。 |
【音の種類別】屋根裏に侵入した害獣の見分け方

先ほど解説したとおり、多くの害獣は夜行性で日没から深夜、長ければ明け方まで活動しています。つまり、行動時間帯だけでどの動物であるかを特定するのは非常に難しいのです。
屋根裏に侵入した害獣を見分けたいときに、大きなヒントとなるのが「音」です。ひとくちに害獣といっても、足音や羽音はさまざま。聞こえる音をたよりに、住み着いている害獣を特定しましょう。
ドタドタ・ドスンという足音を出す害獣
屋根裏から足音が聞こえる場合、下記のような中型以上の害獣の可能性が高いでしょう。
- ハクビシン
- アライグマ
- イタチ
- たぬき
とくにドタドタ、ドスンドスンと“足音だとはっきり分かるほど大きな音”が聞こえる場合、アライグマやハクビシンの足音だと考えられます。足音に加えて、カーやキッキッという高い鳴き声が聞こえた場合はハクビシンだと特定できるでしょう。
反対に、軽くて小さな足音の場合はイタチやたぬきの可能性が考えられます。どちらも頻繁に鳴く動物ではありませんが、繁殖期や威嚇時には鳴き声を出すこともあります。イタチであればキーやクククという鳴き声が、たぬきはヴーという低い音が特徴です。
カツカツ・ガリガリと木材をかじるような音を出す害獣
カツカツ、ガリガリ、ギーギーなど、鳴き声や足音とも異なる特徴的な音が聞こえる場合はネズミと考えてほぼ間違いないでしょう。これは、ネズミが屋根裏にある柱や床材をかじっている音。放置すると家屋の腐食や傾きなどの原因になるため、早めの対処が必要です。このほか、キュッキュッといった甲高い鳴き声、カサカサと動き回るような小さな足音もネズミの特徴です。
バタバタ・カサカサと羽ばたくような音を出す害獣
屋根裏から羽を動かすようなバサバサ、カサカサという音やトンッという小さな音(壁や柱に止まるときの音)が聞こえる場合、コウモリが住み着いている可能性が高いでしょう。羽音があるかわりに、ほかの害獣のような足音が聞こえないことも大きな特徴です。キキキーやキュッキュという鳴き声を出す場合も多いですが、ネズミの鳴き声と類似しており、鳴き声だけでの判別は難しくなっています。
屋根裏に侵入した害獣を追い出す際は鳥獣保護管理法に注意
騒音や悪臭を放つ害獣は、いち早く追い出してしまいたいもの。羽音や足音、活動時間帯などによって特定できた場合は、適切な方法で追い出しましょう。ただし、ここで注意すべきなのが「鳥獣保護管理法」という法律です。知らずに行動してしまうと、うっかり法律違反を犯してしまうかもしれません。
鳥獣保護管理法の概要や、捕獲が禁止されている害獣について確認しておきましょう。
鳥獣保護管理法とは?
鳥獣保護管理法の正式名称は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」といい、その名のとおり鳥獣の保護や管理、狩猟の生活環境の保全、狩猟の適正化を目指して設けられている法律です。具体的には鳥獣の捕獲などの規制、鳥獣捕獲等事業の認定、狩猟制度などに関する内容が規定されています。
鳥獣保護管理法の対象害獣を駆除する場合は、行政へ駆除に関する書面や図面などを提出しなければなりません。
鳥獣保護管理法により捕獲が禁止されている害獣
基本的に、鳥類や哺乳類に属するすべての野生生物が鳥獣保護管理法により捕獲が禁止されています。つまり、本記事で紹介したネズミやイタチ、たぬき、アライグマ、ハクビシン、コウモリなどはすべて捕獲・駆除に許可をとる必要があるのです。ただし例外もあり、環境衛生に著しい影響を及ぼすドブネズミやクマネズミ、ハツカネズミなどは保護の対象ではありません。
屋根裏に侵入した害獣に関するQ&A

最後に、屋根裏に侵入した害獣についての疑問をQ&A形式でお答えします。
活動時間帯や音以外での見分け方は、害獣の種類を特定するうえで大きなヒントになります。屋根裏に住み着いた害獣の被害に悩まされている方はぜひチェックしてくださいね。


更新日
2023.12.26
公開日
2023.12.26
人目が届かず雨風をしのげる屋根裏は、動物にとって格好の住処。そのため、家のわずかな隙間から動物が侵入し屋根裏にネズミやたぬき、イタチなどが住み着いてしまうことがあります。しかし「そのうち出ていくだろう」と放置してしまうと、動物が繁殖して増えたり、悪臭や健康被害に遭ったりする可能性も。そこで今回は、屋根裏に住み着く6種類の動物の見分け方や追い出し方について紹介します。また、屋根裏に動物が住み着いて…

屋根裏に侵入した害獣を追い出したい場合は業者へ相談しよう
屋根裏に害獣が侵入すると、騒音や悪臭、家屋の腐食などに悩まされます。すぐに追い出したいものですが、行政の許可を取る手間もかかるうえ、ハクビシンやアライグマ、コウモリなどの場合は鋭い爪や歯で攻撃される可能性もあります。安全かつ確実に害獣を追い出したい場合は、専門業者に依頼するのが賢明です。当サイトでは信頼できる害獣駆除業者について紹介しています。業者選びに迷った際は、ぜひ参考にしてみてください。