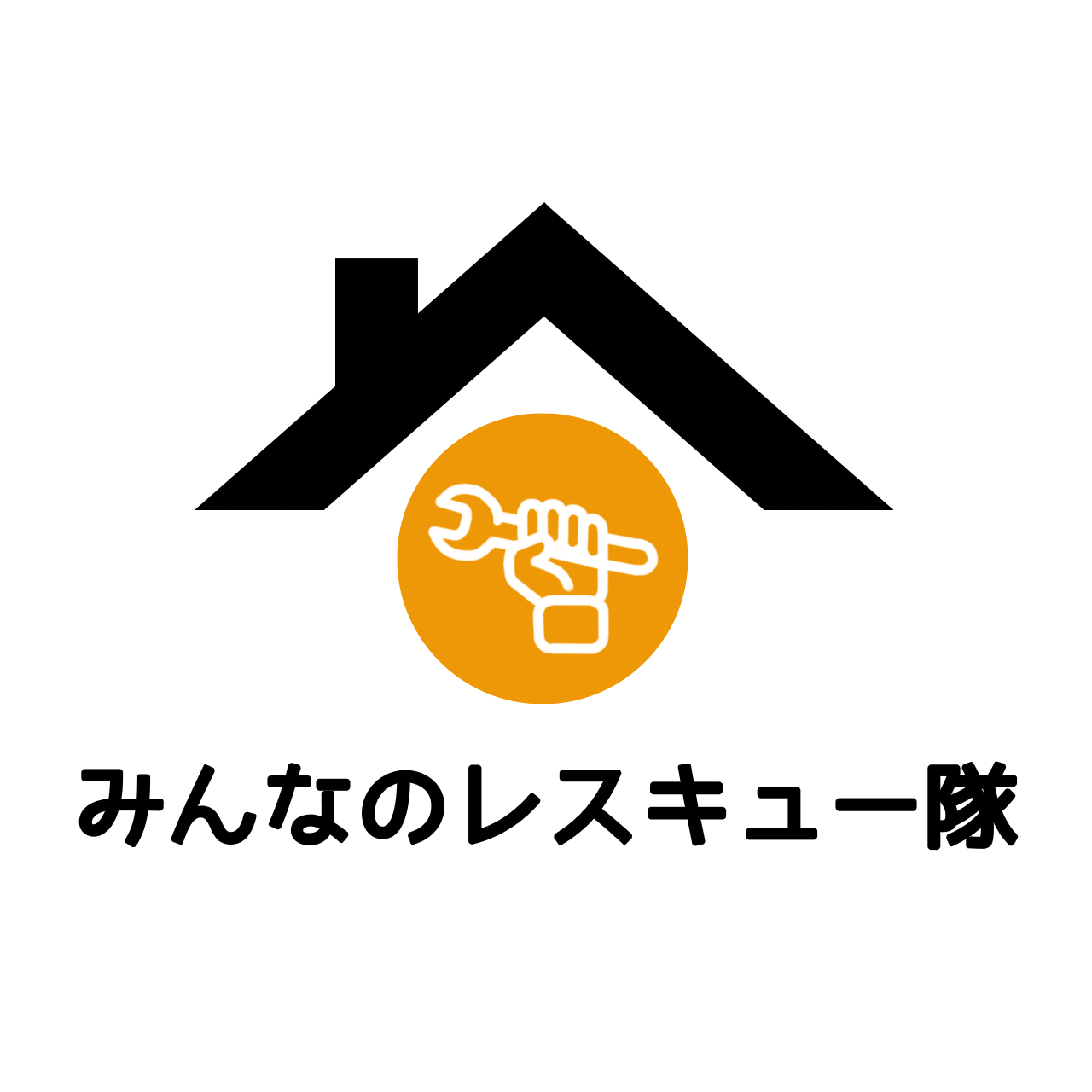コウモリは、屋根裏などに住み着く場合があります。
住み着いたとしても人に危害を与える可能性は低いのですが、フンには病原菌が含まれている可能性があるため注意が必要です。
ここでは、コウモリのフンがもたらす健康被害に焦点を当てています。
フンに含まれる病原菌の種類や、どんな病気リスクがあるのか詳しく解説します。
フンを処理する方法や、自分での処理に不安があるときの対処法についても詳細に説明していますので、最後までご確認ください。
コウモリのフンと関連する健康被害を正しく理解し、最適な処理をしましょう。
コウモリのフンによる健康被害
コウモリの糞には、病原菌が含まれている可能性や、害虫が発生する可能性があります。
なぜ病原菌や害虫リスクがあるのか、具体的に解説します。
【ウイルスが含まれている可能性あり】
コウモリは、人に感染する恐れのあるウイルスを保有している場合があります。
例えば、エボラ出血熱・MERS・狂犬病などのウイルスです。
コウモリがウイルスを保有していると、フンを通して人に感染する可能性があります。
コウモリを媒介にMERSウイルスに感染すると、呼吸器疾患を発症しやすくなります。
免疫力が低下している人は、最悪の場合死に至るケースもあるため、注意が必要です。
また、エボラ出血熱や狂犬病のウイルスも、人に感染すると重症化することがあるので、コウモリに近づく際には注意しましょう。
【吸引して健康被害のリスクがある】
コウモリのフンは、乾燥しやすく微粒子になって空気中を漂います。
人が直接コウモリに近づかなくても、空気を通して病原菌に感染する可能性があります。
特に、コウモリを駆除した後、フンの掃除の際には、作業者が病原菌を吸い込むリスクがあるため注意が必要です。
【害虫が発生するリスクがある】
屋根裏などにコウモリが住み着くと、毎日大量のフンをします。
フンには、ノミ・ダニ・ゴキブリ・ハエなどの害虫が寄ってくるため注意が必要です。
害虫自体が病原菌を持っている可能性があります。
コウモリのフンが原因といわれる病気の事例
コウモリのフンが原因となる病気には、アレルギーや感染症に注意が必要です。
リスクが高いのはアレルギーで、感染症は稀ですが、以下で詳しく解説します。
【アレルギー】
コウモリのフンは空気中に漂うため、吸い込んだ人はアレルギーリスクがあります。
特に、動物に対するアレルギーがある人や、動物の影響で喘息にかかっている人は注意が必要です。
【ヒストプラズマ症】
コウモリのフンから起きる可能性のある感染症のひとつは、ヒストプラズマ症です。
フンに含まれるカビの胞子を吸い込むことで発症します。
免疫力が高い人はカビの胞子を吸い込んでも発症しない場合もありますが、吸い込むこと自体が気になる人もいるかもしれません。
ヒストプラズマ症を発症すると、発熱や咳など、風邪に似た症状が起こります。
重症化すると肺炎を発症してしまうため、注意が必要です。
日本ではコウモリのフンの影響で、ヒストプラズマ症にかかった事例はありません。
しかし、海外では発症例があり、国内でも感染する可能性はあります。
また、コウモリのフンに含まれるウイルスによる感染症としては、狂犬病やアルボウイルス感染症も含まれます。
コウモリのフンの見分け方
コウモリのフンは、ネズミのフンとよく似ています。
ぱっと見ただけで区別は困難ですが、色や質感、発生する場所を見るとわかります。
ネズミのフンの大きさは6mm~1cm程度で、細長い形状です。
一方で、コウモリのフンは5mm~1cmと小さめで、途中でねじれているのが特徴です。
色は、ネズミのフンはこげ茶や灰色で、コウモリは黒色をしています。
湿っているのがネズミのフンで、カサカサと乾いているのがコウモリのフンです。
また、フンが見つかる場所にも違いがあります。
ネズミは動き回りながら幅広い場所でフンをするのに対し、コウモリは1か所に溜めます。
床に落ちているのはネズミで、壁に付着している場合はコウモリのフンです。
コウモリとネズミのフンはよく似ていますが、細かい部分も観察すれば見分けられます。
どちらのフンなのか迷うときでも、質感やフンが見つかる場所を確認すると、区別できるでしょう。
病気にならないようにコウモリのフンを処理する方法
コウモリのフンには病気リスクのあるウイルスや菌などが付着している可能性があるので、フンを処理する際には、病気予防のための対策を行いましょう。
処理の際に準備したいものと、フンの処理のコツを解説します。
【準備するもの】
コウモリのフンを吸い込まないように、ゴーグル・マスクを用意します。
感染予防のため、マスクは防塵マスクが最適です。
他にも、汚れても良いように、使い捨ての服・ゴム手袋を用意します。
併せて、髪が長い人はまとめるヘアゴムや、帽子なども準備してください。
コウモリのフンを処置する際には、ホウキ・チリトリ・ゴミ袋も用意しましょう。
最後に消毒が必要なため、殺菌スプレーや拭き取るための雑巾も用意しておきます。
病原菌の付着の恐れがあるものは使い捨てにしたいので、ホウキ・チリトリ・雑巾は100均のものがおすすめです。
【フンの掃除手順】
コウモリのフンは乾燥しており空気中に舞うので、フンが軽く湿る程度に、殺菌スプレーをかけておきます。
ホウキでフンを集めたら、チリトリですくい取り、ゴミ袋の中に入れましょう。
すべてのフンをゴミ袋に入れたら、口をきっちり縛ってください。
フンは掃除機で吸い取りたくなりますが、絶対に避けてください。
掃除機本体やフィルターに病原菌が付着する恐れがあり、また掃除機の排気口から病原菌を空気中にまき散らす可能性があるためです。
【消毒を忘れずに】
すべてのフンを処理したら、殺菌スプレーで消毒しておきます。
フンがあった部分には病原菌やウイルスが残っている可能性があるため、殺菌スプレーをかけてから、雑巾で拭き取ってください。
続いて、再びコウモリが入り込まないように、侵入経路は金網などで覆います。
小さな隙間があるときは、そこから再びコウモリが侵入しないように、シーリング材やパテでふさぎましょう。
すべての作業が終わったら、使用した道具や使い捨ての衣類もゴミ袋に入れて捨てます。
コウモリのフンを適切に処理して病気を防ごう
コウモリを追い出す際には、フンの処理も必要です。
フンには病原菌が含まれている可能性があるため、感染対策を行い処置しましょう。
自分で処理するのが不安なときは、専門業者の依頼がおすすめです。
コウモリ駆除の専門業者は、作業に慣れており、必要な道具も持っているため、万全の対策で処置ができます。
専門業者に依頼するときは、複数の会社で見積もりを取りましょう。
価格の安さだけでなく、しっかり駆除できるのか、再発防止策はしてくれるのか確認しておくと、安心して任せられる業者が見つかります。