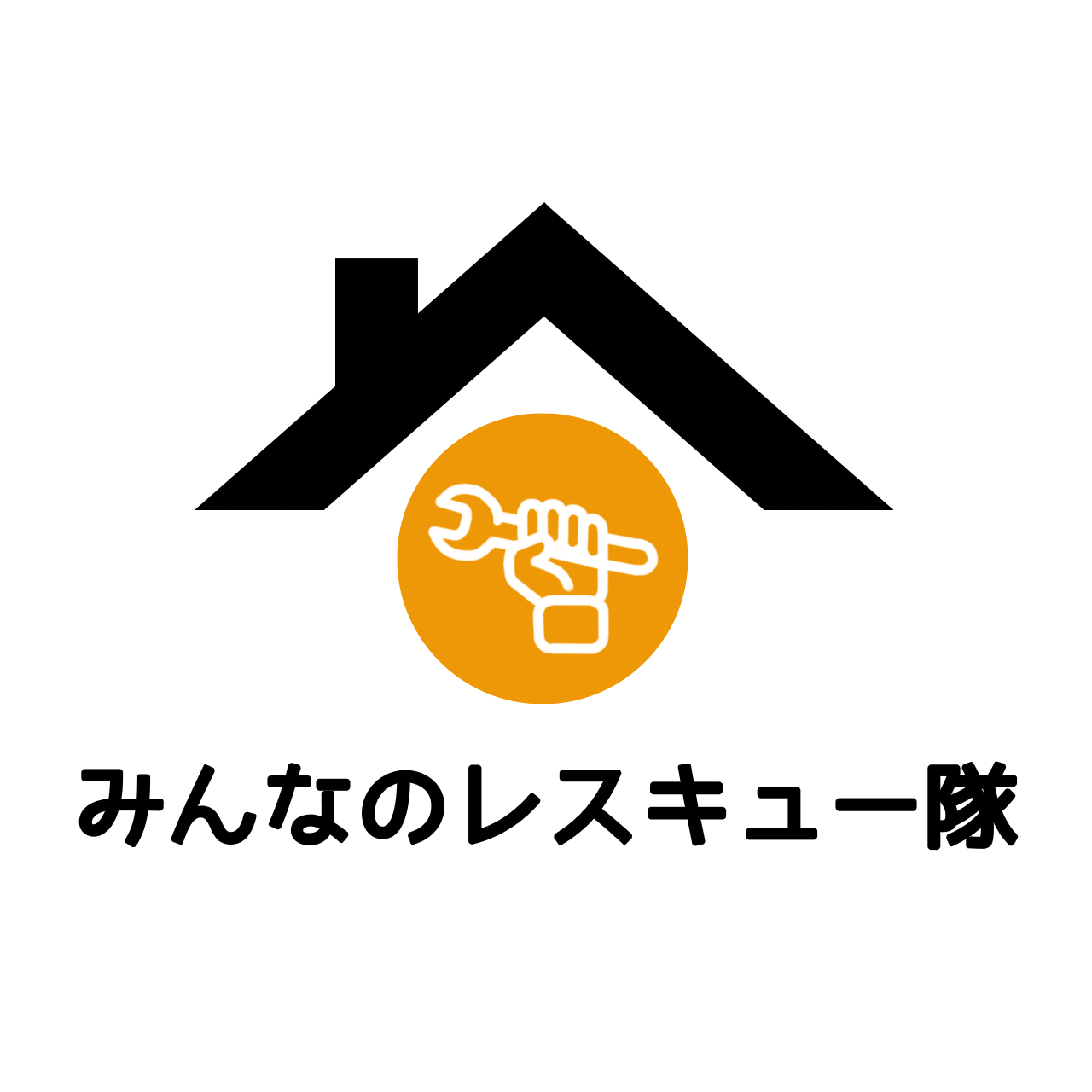ネズミの糞尿は病原菌を媒介するため、見つけたら適切な方法で処理する必要があります。この記事では、家ネズミの種類別に糞の特徴や発見されやすい場所、正しい糞尿処理方法、ネズミの糞尿が媒介する病原菌などをお伝えしています。あわせて、糞尿処理時の注意点についても詳しく解説しているため、ネズミによる被害にお悩みの方は必見です。
【画像付き】ネズミの種類別|糞の特徴

「普段は見かけない小さな黒い糞のような塊がある」「自宅の特定の場所で動物の糞のようなものを見かけるようになった」このような場合、ネズミがご自宅に住み着いている可能性があります。
日本の家屋に侵入する家ネズミ(ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ)の種類別に糞の特徴を紹介します。
ドブネズミ
| 大きさ | 10〜20mm |
|---|---|
| 形状 | 太い楕円形 |
| 色 | 灰色やこげ茶 |
| 発見されやすい場所 | 台所や排水管周り、ゴミ捨て場、下水周辺 |
| その他特徴 | まとまって糞が落ちていることが多い |
ドブネズミは家ネズミの中でも体が一番大きく、糞の長さは10〜20mmにもなります。太い楕円形で糞がまとまっているのが特徴です。
低音に強く泳ぎも得意なドブネズミの糞は台所や排水管、トイレなどの水回りでよく見かけられます。
クマネズミ
| 大きさ | 6〜10mm |
|---|---|
| 形状 | 細長い楕円形 |
| 色 | 灰色や茶色 |
| 発見されやすい場所 | 屋根裏や天井裏、ベランダ、ビルなどの高層階 |
| その他特徴 | 広範囲に糞が散らばっていることが多い |
穀物や果物を好むクマネズミの糞は細長い楕円形で、色は灰色や茶色をしています。
クマネズミは壁や配管を上る習性があるため高層階にも侵入でき、屋根裏や天井裏、高層ビルなどに生息している場合がほとんどです。高層階で広範囲に散らばった6〜10mm程度の糞を見つけたらクマネズミが住み着いている可能性が高いでしょう。
ハツカネズミ
| 大きさ | 4〜7mm |
|---|---|
| 形状 | 両端が尖っていて細長い |
| 色 | 茶色 |
| 発見されやすい場所 | 物置や倉庫、農耕地など |
| その他特徴 | 小さな糞が散らばっていることが多い |
家ネズミの中でも一番小さいハツカネズミの糞は4〜7mm程度で、両端が尖っているのが特徴です。
乾燥に強いため水気のない物置や倉庫を住処とし、都心よりも郊外や農耕地に住み着く傾向があります。乾燥した場所で散らばった小さな糞を見かけたらハツカネズミが住み着いていることを疑いましょう。
ネズミの糞と間違われやすい糞をする害獣とは?
家ネズミの糞と間違われやすいのが下記の害獣による糞です。
- アブラコウモリ
- イタチ
- ゴキブリ
- トコジラミ
アブラコウモリとネズミの糞の大きな違いは、質感です。乾燥していて糞の中に昆虫の足や表皮などが入り混じっている場合、ネズミの糞ではなくアブラコウモリの糞だと考えられるでしょう。
イタチはクマネズミのように天井裏に生息する害獣であるものの、まとめて排泄する習性があります。天井裏で害獣の糞を見つけたら、糞が散らばっているのかそれとも小さな範囲にまとまっているのかに注目するのがポイントです。
台所など水回りで糞を見つけたらネズミではなく、ゴキブリの糞である可能性も否定できません。見分け方に迷ったら糞の大きさに注目してみましょう。水回りを好むドブネズミの糞は10〜20mm程度とインパクトがあるものの、ゴキブリの糞は大きくても2.5mm程度です。注視して探さないと、ホコリと間違えてしまうこともあるほど小さいのがゴキブリの糞の特徴と言えます。
南京虫とも呼ばれるトコジラミは人や動物の血液を吸う習性があるため、糞は赤っぽい色をしています。またネズミの糞は固体であるものの、トコジラミの糞は液体上で排出され時間が経つと固まるためシミが残る点が特徴的です。糞の周辺に赤褐色のシミが付着していたらネズミではなくトコジラミによる被害を疑いましょう。
ネズミの糞を見つけた際の正しい糞尿処理方法
ネズミの糞尿を見つけたら下記の流れで処理しましょう。
具体的には下記の道具があると、ネズミの糞尿処理が原因で病気に感染するのを防ぎやすくなります。
洋服に病原菌が付着するのを防ぐためにも、雨カッパなど使い捨てできる防護服を用意するのがおすすめです。糞を一箇所に集めて処分したら消毒液を噴射し、拭き取ります。万が一、キッチンでネズミの糞が見つかった場合は糞尿の周辺に保管していた食器類も消毒するのが鉄則です。
ネズミの糞から感染する可能性のある病気
ネズミの糞にはさまざまな病原体や雑菌が含まれています。屋内でネズミの糞を見かけたまま放置しておくと病気を発症する恐れがあるため、衛生環境が悪化するのは言うまでもありません。
具体的にネズミの糞がどのような病原菌を媒介するのか確認してみましょう。
サルモネラ菌
サルモネラ菌は嘔吐や下痢、全身の倦怠感を引き起こす原因となります。ネズミの糞を介して食べ物などに付着すると経口感染する可能性があり、乳幼児や高齢者は重症化しやすいと言われているため注意が必要です。
レプトスピラ菌
レプトスピラ菌は頭痛や悪寒、せきなど風邪と似たような症状を引き起こす原因となります。ネズミの糞尿により汚染された水や土壌を介して、粘膜などから感染するのが一般的です。人だけでなくペットへの感染も報告されているため、犬や猫がいるご家庭では特に注意が必要でしょう。
ハンタウイルス
ハンタウイルスは感染すると嘔吐やめまい、発熱などを引き起こす原因となります。ネズミの糞尿を吸い込むことで感染する恐れがあり、感染すると重症化する危険性を伴うと言われています。
ネズミの糞尿処理時に病原菌に触れないための注意点

ネズミの糞尿処理が原因で病気に感染しないためにも、これからお伝えする注意点に目を通しておきましょう。
病原菌に直に触れないようにする
ネズミの糞尿処理の基本は、直に触れないようにすることです。雨カッパなどを着用した上でゴム手袋、マスク、保護メガネを装着し病原菌に触れてしまう可能性を低くしましょう。万が一、ゴム手袋がない場合はティッシュを重ねて糞尿を処理し、素手で触らないように工夫する必要があります。
また、ネズミの糞尿処理時に空気中に舞った病原菌を吸い込まないためにも必ずマスクをつけて鼻や口を覆うことも重要です。その上で保護メガネを着用し粘膜からの感染を防ぎましょう。
掃除機で糞を吸わない
ネズミの糞が広範囲に散らばっている場合、掃除機で吸引したくなるでしょう。しかし掃除機に病原菌が付着すると、家中に病原菌を撒き散らしてしまう可能性があります。また掃除機の排気口を通して病原菌が空気中に飛散する原因ともなり得るため、掃除機の使用は厳禁です。
糞尿があった場所を消毒・除菌する
ネズミの糞尿があった場所をエタノールやアルコールで消毒、除菌しましょう。その際、食毒液を噴射した箇所を拭き取った雑巾などは使いまわさず、処理するのが基本です。
処理前に糞尿の写真を撮影する
ネズミの糞尿を見つけたら処理前に、写真に納めておきましょう。糞尿や発見箇所の写真があれば、ネズミ駆除の専門業者に依頼する際、侵入経路などを発見する手がかりになるかもしれません。
ネズミの糞尿対策は自宅に侵入させないこと
繁殖力の強いネズミの糞尿対策は、自宅に侵入させないことです。自宅にネズミが住み着いている場合、糞尿を処理してもすぐに汚れが目立つようになるため際限がありません。ネズミが繁殖すると衛生環境の悪化だけでなく、コードや木材をかじられるなど電化製品や家屋への損害も否定できません。
糞尿処理だけでなくネズミの侵入経路を塞ぐ方法についても正しく理解することで、ネズミによる被害から身を守りましょう。下記の記事では、ネズミの侵入経路や自宅への侵入を防ぐ方法について詳しく解説しているので、ご覧ください。


更新日
2024.02.02
公開日
2024.02.02
天井裏から木材をかじるような音が聞こえたり食料品にかじられたりした痕跡がある場合、ネズミが住み着いているかもしれません。この記事では、ネズミが建物に侵入する経路や、狙われやすい侵入口、侵入口を塞ぐ方法などを紹介。 「我が家にネズミが住み着いているかどうか知りたい」という方向けに、ご自宅にネズミがいるか確かめる鍵となるラットサインについても解説します。繁殖したネズミによって被害を受ける前に侵…

ネズミの糞を見つけたら正しい方法で処理しよう
ネズミの糞を見つけたら決して素手で触らず、皮膚や粘膜を保護した上で処理に当たりましょう。
「何度か糞尿処理したのに、また糞が溜まっている」「糞尿による被害が心配」このような場合は、一度ネズミ駆除の専門業者に相談してみるのもおすすめです。頼れるプロに相談すれば、侵入経路について調査した上でネズミの糞尿処理から消毒まで対応してもらえるでしょう。ネズミの糞尿処理が原因で感染症を引き起こす心配からも解放されます。
当サイトでは、信頼できる優良ネズミ駆除業者をまとめて紹介しています。お住まいの地域から地域の専門業者を検索できるので、ぜひご活用ください。