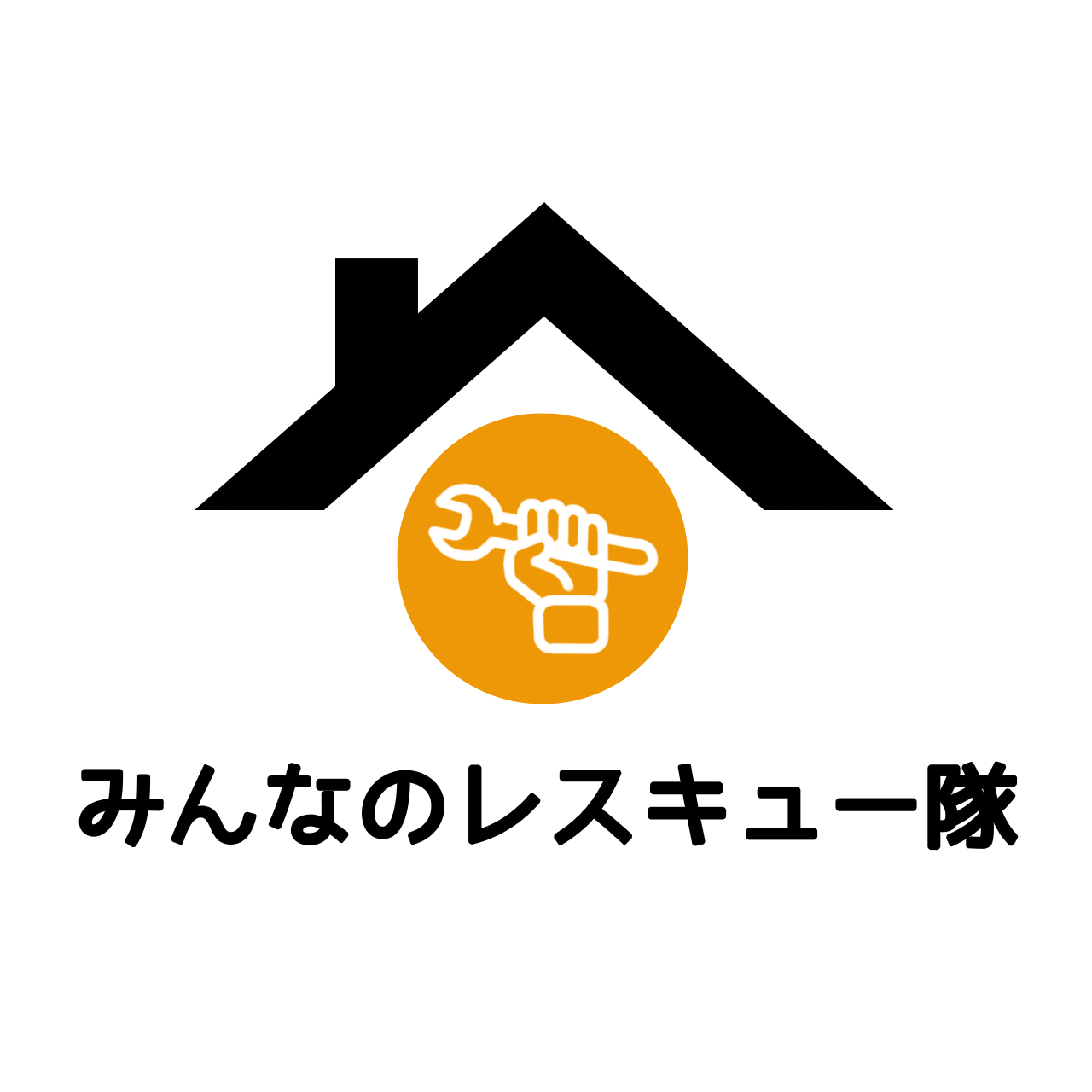アシナガバチの巣は家屋の軒下や樹木など、身近な場所に作られることが多く、安全面や美観の面から問題となることがあります。アシナガバチの生態を理解し、適切な対策を講じることで、巣の形成を防ぎ、快適な生活環境を維持することができます。
本コラムでは、アシナガバチの生態や習性を解説し、効果的な蜂の巣対策について詳しく説明します。
アシナガバチの習性と巣作りの場所
アシナガバチは体長が約21~26mmで、スズメバチに似ていますが、足が黄色いのが特徴です。巣の特徴は、お椀を逆さにしたような半円の形をしています。
アシナガバチの活動時間帯は、暖かく視界が良い昼間です。夜間は気温が低下するため蜂の体温も下がります。また、暗いため視界が悪いことから行動が鈍くなります。
アシナガバチの年間行動としては、4月頃に女王蜂が巣作りを始め、5~6月頃に働き蜂が巣を大きくします。7~8月頃は巣作りの最盛期で、9月が巣作りの最終段階です。10月からは、新女王蜂のみ越冬し、翌年4月頃からまた女王蜂が巣作りをするサイクルとなっています。
蜂の危険な時期は、最大活動期の8~10月です。この時期にアシナガバチはスズメバチとの縄張り争いが活発化し、特に警戒を強めます。気づかずに巣や蜂を刺激すると、攻撃される可能性がありますので、注意が必要です。
アシナガバチの巣は、雨風が当たらない風通しの良い場所に作られます。そのため、民家の軒下やベランダ、物置など、人間の生活空間に近い場所に巣を作ることが多いです。他にも庭木や街路樹の枝やエアコンの室外機にも巣を作ることもありますので、注意してください。
アシナガバチの巣を作らせないようにする方法
アシナガバチの巣作りを防ぐためには、以下のような予防策が効果的です。
■定期的な点検と清掃
蜂の巣を作らせないように、定期的な点検と清掃を行いましょう。アシナガバチは人通りの少ない場所を好んで巣作りをします。使用していない物置なども定期的な清掃をしておきましょう。キレイな状態を保つことで、巣作りをさせない予防になります。3月頃~6月頃までは、特に注意が必要です。家のまわりに巣を作っていないか、注意深くチェックをしましょう。
■潜在的な巣作り場所の封鎖
蜂の侵入をブロックするために、蜂が入って来やすいベランダや換気扇に防虫ネットを取り付けてください。蜂が通り抜けられない程度の網目であれば問題ありません。
■女王蜂を退治する
初めに巣作りをするのは女王蜂です。この女王蜂を蜂トラップで捕獲することで巣を作らせなくさせます。蜂トラップには誘引液のニオイにつられてきた蜂をトラップの中に閉じ込めて出られないように捕獲するものです。この蜂トラップを巣が作られる前に設置し、4月頃には撤去をしてください。撤去をしないで放置していると、働き蜂が匂いで寄ってくるため、刺される危険性が高くなります。
■殺虫剤を使う
予防効果のある蜂用殺虫スプレーを定期的にしておくと効果的です。注意点は、雨が降ると殺虫剤は流れてしい効果が弱まるため、雨後に再度蜂用殺虫スプレーをする必要があります。他にも、庭で植物を育てている場合、殺虫スプレーを使い過ぎると悪影響を与える可能性があるので注意が必要になります。
■木酢液で予防する
木酢液も蜂の巣予防には効果的です。木酢液は焦げ臭いがする刺激臭が特徴的です。蜂はこの刺激臭が苦手なので、木酢液を使用することで寄せつけない効果があります。
■業者に予防を依頼する
費用はかかりますが、根本的な解決をするならプロの専門業者に依頼する方法もあります。
このような方法を試してみると、アシナガバチの巣作りを阻止できるでしょう。
アシナガバチに巣を作られた場合の対処法
ここでは、アシナガバチの巣を発見したときの対処法について解説します。
■自分で対処する場合の注意点と方法
6月頃までの10cm程度の小さい巣なら、自分で駆除できる場合もあります。ご自身で駆除できる基準としては、巣の高さが2~3mほどで十分にスプレーが届く距離であること、軒下や庭木など開放的な場所にある場合などです。
防護服・殺虫剤を用意して、アシナガバチの活動が鈍い夜間に駆除作業を行いましょう。巣から離れた風上側から風下にある巣に対して、斜め下の角度から殺虫剤を一定時間吹きかけると安全で効果的です。
吹きかけてから1日置いて、生きている蜂がいなければ問題ありません。死んでいることが確認できても処理する前に念のため再度殺虫剤を吹きかけましょう。蜂は死んでも針に毒がありますので、「トング」または「ほうきとちりとり」などを使用して巣や蜂を新聞紙などで包みましょう。その後、ポリ袋などに入れて密封し燃えるゴミに出してください。
■専門業者に依頼する場合
7月以降、アシナガバチの巣は大きくなってしまうため、ご自身で駆除するのは非常に危険です。危険な巣の駆除はプロの専門業者に依頼することをおすすめします。駆除費用については、巣の大きさや巣の場所によりますので、見積もりを複数社に依頼し、信用できる業者に依頼しましょう。
アシナガバチの巣が小さいうちは自分で駆除することも可能ですが、危険が伴いますので十分に気を付けて行う必要があります。また、駆除が難しい場合は、無理せず専門業者に依頼しましょう。
アシナガバチの巣作りの予防を専門業者に依頼するメリット
害虫駆除の専門業者は、駆除に必要な知識と経験を持っており、より安全で効果的な設備で問題を解決することができます。専門業者に依頼するメリットとして、下記が挙げられます。
・最新の駆除技術と専用機材を使用して、迅速かつ効率的に巣を除去する
・自分で行う必要が無いので、駆除中の事故や怪我のリスクがない
・駆除後の再発防止措置をしてくれるので安心できる
このように、専門業者に依頼すると確実な解決が期待できます。もし、ご自身での駆除に自信がない場合や大きくなってしまったアシナガバチの巣の駆除、見えない場所の巣の駆除が必要な場合は、迷わず専門業者に依頼することをおすすめします。
アシナガバチの巣を作らせないためには日常的な点検と予防が大切
アシナガバチの巣を作らせないためには、3月頃からの点検や予防対策、清掃が不可欠です。もし、ご自身での対処が難しい場合や巣が大きくなってしまった場合は、専門業者に相談しましょう。
また、お住いの住居が賃貸物件の場合は、必ず管理会社やオーナーにすぐ連絡をしてください。ご自身での対応や専門業者への依頼は、後日トラブルになる可能性がため、十分に注意が必要です。