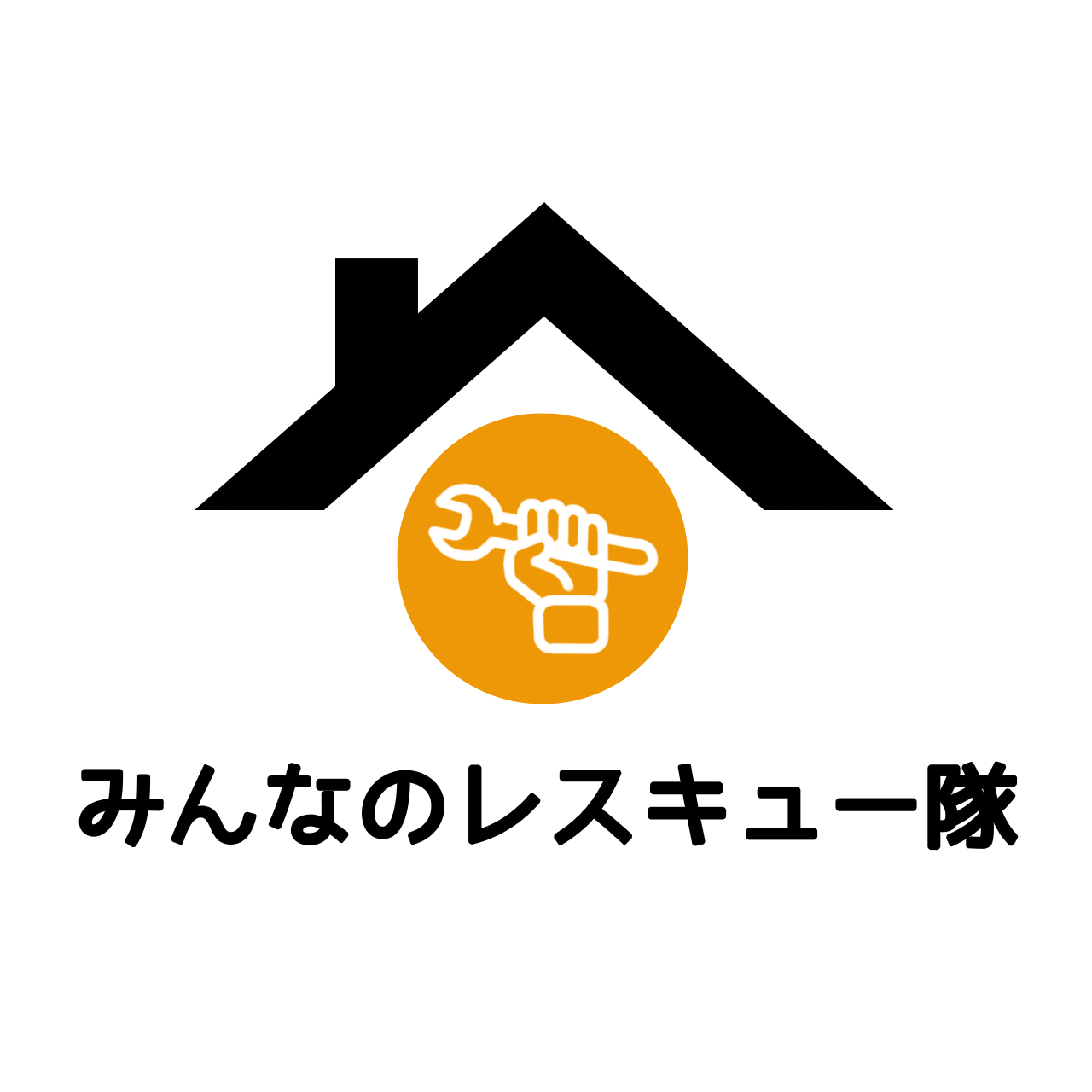マイホームを持っている方にとって、シロアリは脅威と言える存在。シロアリによって柱や土台が侵食されてしまうと、建物の倒壊リスクが高まります。大切な家にシロアリを寄せ付けないためには、日々の生活の中での予防が欠かせません。
本記事では、シロアリが来ない家の特徴について解説します。また、シロアリが出やすい家の傾向や築年数の浅い今時の家にも予防対策は必要なのか否かについても紹介しているため、シロアリ対策に悩まれている方は参考にしてください。
シロアリが来ない・好かれにくい家の特徴
シロアリには好む環境と好まない環境があります。ご自宅はシロアリにとってどのような住環境でしょうか。ここではシロアリが来ない、好かれにくい家にみられる特徴を解説します。
湿気対策がなされている
シロアリが来ない家の多くは、除湿器を使って湿度を調整したり換気設備を設置したりするなど、湿気対策がなされています。また近頃はシロアリや木材腐朽を防ぐ対策として、家づくりの段階から配慮しているケースも見られます。
例えば、空気がこもりがちな下駄箱やクローゼットにはあえて扉を設けなかったり、24時間換気システムのなかでも結露が発生しにくいよう設計された高機能な設備を導入していたり。ほかにも、湿気に強い壁紙や床材を採用することもシロアリが好まない環境作りへとつながります。
基礎工事がしっかりしている
シロアリが来ない家の条件に、基礎工事がしっかりしているという特徴が挙げられます。戸建ての基礎は、地面が部分的に露出している構造もありますが、鉄筋コンクリートで全面的に覆ったベタ基礎と呼ばれる構造は、地面の露出が少なくシロアリ被害が出にくいとされています。しかし、経年変化によってヒビ割れが生じたわずかな隙間から床下へ侵入することもあるため注意が必要です。
また床下は湿気が溜まりやすい場所であるものの、基礎に十分な高さが確保できている家はシロアリが出にくい傾向にあります。高さが確保できていないと定期点検が行いにくいため、シロアリの発見が遅れてしまう可能性もあるでしょう。
雨漏りしにくい外壁材を使用している
シロアリが来ない家は、外壁や屋根など雨漏りしにくい素材にこだわっていることも多いです。雨漏りが発生すると、木材を腐食させる恐れがあるだけでなく、湿気が多くなることからシロアリを繁殖させる原因になり得ます。タイル外壁や瓦屋根は雨漏りしにくい素材なので、これから家を建てる方は検討材料のひとつにしてみましょう。
廃材などが散らかっていない
敷地内に木材やダンボール、古新聞などを放置しないこともシロアリが来ない家にみられる特徴です。シロアリが食べるのは木材だけだと思っていないでしょうか。実は、シロアリが食べる餌には紙類も含まれています。湿気の多い場所に放置され、水分を含んで柔らかくなったダンボールや古新聞などはシロアリの大好物です。廃材を放置すると、シロアリをおびきよせてしまう可能性が高まります。
周辺環境でわかるシロアリが出やすい家とは?

シロアリが発生する原因は、建物の構造のみが関係しているとは限りません。住宅が建っている周辺の環境によってシロアリ被害が起きてしまう場合もあります。次のような環境が周りにある住宅は要注意です。ご自宅の周辺は安心できる環境かぜひチェックしてみてください。
日当たりが悪い
日当たりが悪い場所に位置している家は、シロアリが出やすい傾向があります。シロアリは日光に弱い生物で、ジメジメとした場所を好む性質があるため、地面や外壁などにコケが生えている場合はシロアリが生息している可能性も。特に建物の北側は日が当たりにくく湿度が高いことも多いため、コケができていないか定期的に確認してみましょう。
山間部に建てられている
周りの山よりも低い位置にある山間部は、雨水が流れ込みやすく湿気が溜まりやすいのが特徴です。そのため、山を切り崩して造成された住宅地は、都心にある住宅地と比較するとシロアリが発生しやすい環境にあります。また、山間部でなくても近隣に山や森林が生い茂っているような場所がある場合も要注意。自然が多い場所ほどシロアリの餌も多いため、発生率が高くなります。
川や沼など水辺に近い
近くに川や沼、池や湖などがあるエリアに建つ家も注意が必要です。このような場所はもともと土地に含まれている水分量が多く、湿度の高い場所を好む生態のシロアリには格好の環境となります。また、もともと池や沼があったものの、埋め立てて住宅地として造成した土地も湿度が高めであることが多いです。そのため、日頃からシロアリ対策をしっかりと行いましょう。
自宅にシロアリを寄せ付けないための対策
シロアリは床下や壁の内部など目につきにくいところを食害するケースも多く、気が付いたときには被害範囲が大きくなっている場合も。このような状況を回避するためには、シロアリにとって好ましくない環境作りが大切です。どのような対策が効果的なのか、具体例をいくつか確認してみましょう。
日当たりを良くする
暗くてジメジメとした場所に繁殖しやすいシロアリの対策には、日当たりを良くすることが重要です。敷地内に生えている庭木が生い茂り、日当たりが悪くなっていないでしょうか。木や枝を切り落とすと日当たりが良好になるだけでなく、風通しも良くなります。定期的に手入れしましょう。また家の周りに物を置くと日陰を作ってしまうため、不要なものは置かないようにすることもシロアリ対策には有効です。
定期的に換気する
普段から定期的に室内の換気を意識すると、シロアリを寄せ付けにくくなります。ドアや窓を開けて風通しを良くするよう意識しましょう。また床下や押入れ、下駄箱や納戸なども湿気が溜まりやすい場所です。定期的に風通しを良くしておくとシロアリ対策はもちろん、カビやダニの予防対策にもつながります。
防腐剤や防除剤を使用する
市販されている防腐剤や防除剤を使用して、シロアリの予防対策を行うのもひとつの方法です。床下や庭をはじめ、シロアリが発生しそうな場所に防腐剤や防除剤を適量散布します。防腐剤や防除材によるシロアリ対策は、費用を抑えながら誰でも手軽にできる点が魅力的です。しかし、市販の製品は一般的に約3ヶ月~半年ほどしか効果が持続しないため、こまめに散布する必要があります。
今時の家はシロアリ駆除が必要ない?

シロアリが発生するのは築年数が経った古い木造の家というイメージを持っている方も多いかもしれません。そのため「新築の我が家は大丈夫」「うちはコンクリートでできているから心配ない」と安心していませんか?実際のところはどうなのでしょうか。ここでは新築の家とコンクリートの家に分けて、シロアリ駆除の必要性についてみていきましょう。
新築の場合
一般的には築年数が経過している古い家のほうがシロアリの被害は出やすい傾向にあります。しかし、新築だからといってシロアリの被害に絶対に遭わないとは断言できません。シロアリにとって好ましい環境があれば新築であっても、侵入してくる恐れがあります。例えば断熱材を使用している家は、風通しが悪くなり湿度が高くなってしまう可能性があります。また、近所の家や森林などに住み着いているシロアリが飛んでくることも考えられるでしょう。
しかし新築時、土壌にシロアリの予防工事を請けていて保証期間内、かつシロアリによる初期症状がない場合はそれほど心配する必要はありません。一般的に5年間の保証期間が設定されているケースが多いため、新築5年未満であれば発生リスクは低いと考えられます。シロアリの初期症状については次の記事を参考にしてみてください。初期症状を知っておくことで、シロアリによる被害を食い止められます。


更新日
2023.12.14
公開日
2023.12.15
大切な家屋を食べ荒らし、建物の破損や倒壊の原因となることもあるシロアリによる被害。シロアリは繁殖スピードが驚くほど早く、家に侵入するとあっという間に被害が進行してしまいます。このような状況を防ぐためには、建物に変化や異変がないかこまめに確認することが大切です。そこで今回は、シロアリ被害の初期症状についてまとめてみました。また、シロアリ被害が進行した際に見られる症状やシロアリを見つけた際の対処法、…

シロアリ被害に遭う前に業者に相談しよう
シロアリに侵食されてしまうと耐震性が下がったり、建物の資産価値が下がってしまったりする恐れも。シロアリを発生させないためには、日頃から換気や日当たりなどに気を付けることが大切です。しかし、それでもシロアリを防げない場合もあるでしょう。シロアリは目につきにくい場所に潜んでいることも多く、素人目で発見するのは容易ではありません。
大切な家がシロアリに侵食されて手遅れになる前に、一度プロに相談してみるのも良いでしょう。専門業者に依頼すれば床下の調査や予防対策を丁寧に行ってくれるほか、万が一シロアリがいた場合にはシロアリの種類に見合った薬剤を使用して駆除してくれます。当サイトではシロアリの専門業者を紹介しているため、お困りの際はぜひご活用ください。